活躍の場が広がっているAI・人工知能について学べるAIの学習本。AIに精通した有識者が手がけているモノが多く、曖昧になりがちなAIの知識を体系的に学びやすいのが魅力です。すぐに使える実践的な知識が紹介されている書籍も数多くあります。
今回は、AIの学習におすすめの本をご紹介。初心者・中級者・上級者と、レベル別に手に取りたい学習本をピックアップしました。選び方とあわせて参考にしてみてください。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
AIの学習におすすめの本の選び方
自分のレベルに適した本を選ぶ

By: amazon.co.jp
AIの学習のための本を選ぶ際には、まずは内容が自分のレベルに適しているかどうかを重視しましょう。AIを学ぶための本は多種多様。初心者向けの入門書から実践的な理論や技術に踏み込んだ上級者向けの専門書まで、紹介されている知識レベルには大きな幅があります。
これからAIについて理解を深めていきたい初心者には、どの分野にも共通する根本的な基礎知識を紹介したモノがおすすめ。特にプログラミング未経験の方は専門的な数式やコードの扱いが少なく、イラストや図が多いモノから手に取ってみてください。
AIの基礎的な知識を学習済みの方やプログラミング経験者といった中級以上の方は、具体的な実装例や実習付きの本をチェック。本を読みながらアウトプットを重ねられるモノなら、より学んだ知識が定着しやすくなります。
AIについて知りたい内容で選ぶ

By: amazon.co.jp
AIについて知りたい内容を絞ることも選書を行ううえで重要です。AIの基礎的な概念について解説した本からビジネスでの活用の仕方、特定の技術に特化して使い方を説明した本まで、AIに関する本は扱っている内容も多岐にわたります。
ビジネスでの可能性を考えるなら、活用事例や今後の展望について触れたモノを。AIエンジニアを目指すなら、具体的な実装方法に重点を置いた技術書をチェックしましょう。選書で迷子にならないためにも、まずはAIを用いて何がしたいのかを明確にしておくのがおすすめです。
実践に活かせる内容かを確認する

By: amazon.co.jp
本で紹介されている内容が実践に活かせるかどうか、目次などから確認するのも重要なポイント。実際に使用するツールと本で取り上げられているモノのバージョンが異なったり、自分の業務範囲と離れすぎていたりすると、別の本で学び直すことになってしまいます。
具体的なプロンプト作成のコツや実例が挙げられている書籍なら、AIを利用する際にそのまま取り入れられるのがメリット。実際に手を動かす作業を通して解説するタイプの書籍では、実践する際につまずきやすいポイントや苦手な分野を感覚的に学べます。
最新の情報が掲載されているかをチェック

By: amazon.co.jp
AIに関連する分野は、技術の進化が速いのが特徴。学習する本を選ぶときにも、最新の情報が掲載されているかどうかをチェックしましょう。刊行年が新しいモノなら、最新の手法やモデルについての情報も記載されている可能性が高い傾向にあります。
本質的な理論や設計思想などについて扱った本の場合は、ロングセラーの名著も多数。一方で、具体的なノウハウを扱った本はできるだけ最新のモノを手に取るのがおすすめです。
AIがアップデートされた結果、古い本では学んだ知識が通用しない恐れもあります。人気の書籍の場合は改訂を重ねて刊行されていることも多いため、新版が刊行されていないかどうかも確認してみてください。
AIの学習におすすめの本|初心者向け
池田書店 マンガでわかる人工知能
コンピューターや機械に苦手意識がある方もAIについて理解できるように工夫された、初心者向けの入門書です。人工知能ロボットを活用する新プロジェクトを任された会社員が、AIについて学んでいく様が漫画形式で描かれています。
ディープラーニング・機械学習・シンギュラリティといったAIに関連する用語の意味からていねいに解説。イラスト・図解も交えながら、難しいテーマや概念が噛み砕いて説明されています。AIによって世の中が変化する方向性を掴める1冊です。
AIを使って何ができるのかといった、初心者にとってイメージしにくい根本的な疑問からすくい上げているのが魅力。AIの要の技術や歴史といった、本質的な知識がまとめられています。AIを学習してみたい中学生から読めるおすすめの入門書です。
KADOKAWA 人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの
日本トップクラスの人工知能研究者の1人である著者が、AIとは何かを初心者にもわかりやすく解き明かした人気作です。技術的にどのように進化してきたのかというAIの歴史をていねいに追っていく構成が特徴。AIの本質が専門的な視点で考察されています。
AIの進歩の過程が全7章でわかりやすく整理されている本書。さまざまな知見からAIの発展が語られています。特に、近年のAIにおいて重要なディープラーニングについて詳しく触れられているのがポイントです。
AIが可能なこと・不可能なことを取り上げるとともに、今後のAI分野の展望も予想されています。専門的な予備知識がない初心者も読み物として親しみやすいのが魅力。AIが歩んできた歴史から基礎を学べるおすすめの名著です。
SBクリエイティブ 生成AIで世界はこう変わる
生成AIによって人々の働き方や生活がどのように変わるのかを、AI研究者の視点から紐解いていくAIの学習本です。生成AIの技術革新や歴史に触れながらAIが人間社会に与える影響を考察し、その展望が全5章で詳しく語られています。
生成AIとは何か・AIの背後にある技術・AIが取って代わる仕事といった、AIを扱うにあたって気になるさまざまな疑問別に章立て。具体的にどのような変化と影響があるのかが、生成AIに詳しくない方にもやさしく説明されています。
イラストや音楽といった、クリエイティブ産業にもたらす影響についても独自の考えを述べている本書。生成AIが活躍する時代において、身につけておきたいスキルや考え方も紹介されています。生活やビジネスに活かせる教養としてAIを学びたい方におすすめの注目作です。
SBクリエイティブ この一冊で全部わかる ChatGPT & Copilotの教科書
生成AIの基本知識と実践的な利用方法を網羅的に解説した入門書です。OpenAIが提供している生成AI「ChatGPT」と、Microsoftが開発したAIアシスタントツール「Copilot」の2つに焦点を当て、それぞれの仕組みが深掘りされています。
ChatGPTおよびCopilotの具体的な使い方を取り上げるだけでなく、生成AIの根幹の仕組みから説明していくのが特徴。業務を効率化させる生成AIの使い方や押さえておきたいポイントなど、実務目線に立ったトピックで章立てされているのも魅力です。
ChatGPTとCopilotの違いを理解できるほか、望んだ回答を得るためのプロンプト作成のコツや実用例も掲載。生成AIを扱うにあたって、応用のきく基礎知識を学べます。生成AIを学ぶ一歩目としてもおすすめの本です。
日経BP 生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方
経営層や事業リーダーといった実務家向けに、生成AIの使い方と可能性を紹介した指南書です。事業や組織を成長させるために、生成AIをどのように活用すればよいかを解説しているのがポイント。ビジネス・サービスづくりに生成AIを取り入れるノウハウが語られています。
本書は「事業づくり」「サービスづくり」「組織づくり」の3つのテーマで構成。それぞれの現在と未来、両方の視点から生成AIを絡める方法論が取り上げられています。ノウハウだけでなく、多様な業界の未来予測について触れられているのも特徴です。
各章にはコラムを掲載し、本章の補足や豆知識なども紹介。非エンジニアも理解しやすい生成AIの技術解説や生成AI関連のスタートアップリスト、おすすめのニュースレターリストなども収録されています。生成AIを強みにしたいビジネスパーソン向けの教養書です。
マイクロマガジン社 9歳から知っておきたい AIを味方につける方法
生成AIの仕組みや長所と短所を、子供も楽しく学べる入門書です。”どんな場面で、どのように生成AIを使うといいのか”を理解できるよう編集されている1冊。生成AIとは何かといった素朴な疑問からていねいに解説されています。
楽しく勉強する・創作する・便利な生活を送るといった、AIを使った目的別に全6章で説明。AIが日常のどのような場面で使用されており、今後どのように活用できるのかが、漫画やイラストを交えて紹介されています。
生成AIを使うにあたっての注意事項や危険性にも触れられているのがポイント。小学校高学年の子供が1人で読み進められるよう、本文の多くの漢字にふりがなが振られています。親子でAIを学びたい方はもちろん、教師を務める方にもおすすめの学習本です。
技術評論社 図解即戦力 機械学習&ディープラーニングのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書
図解形式で機械学習とディープラーニングの仕組みを学べる、おすすめの解説書です。両者の基本と関連する技術、さらに開発の基礎知識までひと通り学べることを目的としています。
AI・機械学習の基礎知識にはじまり、それぞれのコア技術・アルゴリズム・システム開発と開発環境まで、まず知っておきたい知識を広く解説。把握しておくべきキーワードを軸に解説が構成されているため、重要な語句と要点を掴みやすいのがメリットです。
フルカラーイラストと図解が豊富に掲載されていることで、わかりにくい概念や技術も視覚的にイメージしやすくなっています。重要な解説文はあらかじめハイライトで強調されており、効率的に学習を進められるのも魅力。エンジニア1年目の方にもおすすめの教本です。
AIの学習におすすめの本|中級者向け
オライリー・ジャパン ゼロから作るDeep Learning ーPythonで学ぶディープラーニングの理論と実装
大量のデータを学習して自動で高度な判断や予測を行うディープラーニングの、本格的な入門書として定評がある1冊。あえて外部のライブラリを使わず、Python3を用いてディープラーニングをゼロから実装しながら解説する方針を採用しています。
実際に手を動かしながら進めることで、ディープラーニングの原理を楽しく学べるのがメリット。ニューラルネットワークの基礎にはじまり、具体的な処理や実践的なテクニックも数多く取り上げられています。
数学的な知識がまだ少ない方も、仕組みを理解できるよう構成されているのもポイント。続編も刊行されており、シリーズを通して段階的に知識を身につけられます。ディープラーニングの全体像を掴むのにおすすめのロングセラー学習本です。
SBクリエイティブ ディープラーニングG検定 ジェネラリスト 最強の合格テキスト 第2版
AIおよびディープラーニングについての技術的な手法やビジネスに活用するための知識の習得度を確認できる、「G検定」の対策テキストです。検定合格のための対策本としてはもちろん、AIやディープラーニングを体系的に学びたい中級者も活用できる内容になっています。
AIやディープラーニングの各分野の知識を、語りかけるような口調でやさしく解説。基礎概念から応用技術・研究分野・プロジェクトに必要な知識まで、AIを扱うにあたって重要な項目が広くまとめられているのが魅力です。
第2版では生成AIや数理統計学について新たな章を設け、法律・倫理関係の解説も充実させています。1冊で解説・問題・模擬試験を一括で取り組めるのもポイント。AIを理解するにあたって知っておきたい知識を一挙に学べる、おすすめの参考書です。
SBクリエイティブ Photoshop & Illustrator & Firefly 生成AIデザイン制作入門ガイド
「Photoshop」「Illustrator」「Firefly」などAdobeが提供するツールを使った、生成AIによるデザイン制作を解説する1冊。Adobeの生成AIをうまく活用するための方法が紹介されています。生成AIの基本から、制作手順・発展的な活用方法まで学べる学習本です。
Adobeの生成AIとは何かという基礎的な知識から、画像の拡張・レタッチ・ベクターデータの作成といった実践的な手法まで幅広く取り上げられています。合計350点以上の作例が挙げられており、デザインのためのアイデア出しとしても参考にできるのが魅力です。
生成AIを扱うにあたっての注意事項を弁護士に尋ねたコラムも収録。生成AIに関連する著作権の扱いについて、知っておくべき知識が簡単にまとめられています。デザイン制作に生成AIを取り入れてみたいという方に、まずおすすめの参考書です。
翔泳社 Python3年生 ディープラーニングのしくみ 体験してわかる!会話でまなべる!
AIで重要なディープラーニングについて、いちから学んでみたいという初心者・中級者におすすめの実践的な学習本です。ディープラーニングの基本的な仕組みを、サンプルを動かしながら学べるのが魅力。Pythonの基本文法を扱える方向けに執筆されています。
各章の冒頭には漫画やイラストを収録。キャラクターがAIにおけるディープラーニングについて学んでいく、会話が主体の解説文が採用されています。文法は必要最低限のモノが厳選されているため、ディープラーニング初心者も取り組みやすい1冊です。
サンプルはWebからダウンロードできます。ディープラーニングの基礎からプログラミングの仕組みまで、開発体験を通して一連の流れを簡単に掴めるのがメリット。ディープラーニング実践の第一歩としてもおすすめです。
翔泳社 Pythonで動かして学ぶ!あたらしい機械学習の教科書 第3版
AI分野で必要とされるプログラミング言語・Pythonを実際に動かしながら、機械学習の基礎を学べる学習本。数式とPythonのプログラムを連携させて解説していく構成が採用されています。機械学習の原理を、数式からしっかりと理解しやすいのがメリットです。
機械学習やPythonの基礎知識を筆頭に、全10章でまとめられています。数学的な原理からプログラムの実装まで、順を追って学べる1冊。文章・数式・Pythonコードの3段階の解説が掲載されており、数式とコードの関連性を把握しやすいのも魅力です。
特に、機械学習に関連する数学の知識がていねいに解説されているのがポイント。AIプログラミングを行うにあたって必要なPythonのライブラリなども紹介されており、実務で役立つ技能を学べます。機械学習とPythonの教本で挫折した経験がある中級者にもおすすめです。
KADOKAWA 人工知能プログラミングのための数学がわかる本
AIのプログラミングに使われる基本的な数学をやさしく学べる学習本です。AIプログラミングに必要な知識に特化しており、専門書を読むための数学の基礎力を養えるのが魅力。AIのアルゴリズムとともに数式の意味も理解できるよう構成されています。
全7章で、中学1年生の数学基礎から「微分」「線形代数」「確率・統計」まで広く解説。「データから住宅価格を推定する」「文学作品を分析する」といった、Pythonのコードを動かす実際の機械学習の題材が取り上げられているのもポイントです。
演習問題や例題なども豊富に掲載されており、初歩から体系的に数学を学び直せる本書。「人工知能ではこう使われる!」と題したコラムも収録し、AIアルゴリズムについての知識が補足されています。AI学習に必要な数学的知識を把握したい方におすすめのテキストです。
マイナビ出版 大規模言語モデルを使いこなすためのプロンプトエンジニアリングの教科書
ChatGPTに代表される「大規模言語モデル」を使う際に理想的な回答をうまく得るための、「プロンプトエンジニアリング」をテーマにした実用的な学習本です。大規模言語モデルの応答能力を改善・向上させるための方法が網羅的に整理されています。
一般的な業務からアプリ開発といった専門的な業務まで活用できるよう、基本から応用まで幅広いテクニックを紹介。高度なプロンプトエンジニアリングの手法を取り入れた、多彩なプログラムの例も取り上げられています。
ChatGPT以外のさまざまな言語モデルにも活用できる、汎用的な技術を学べる1冊。履歴書の生成や業務自動化に便利なプロンプトはテンプレートとしてまとめられています。エンジニアからビジネスパーソンまで、生成AIを効果的に使いこなしたい方におすすめです。
技術評論社 改訂新版 ITエンジニアのための機械学習理論入門
ITエンジニア向けに、AIの機械学習を基礎から理論的に学べるよう執筆されたAIの学習本です。データサイエンスからベイズ推定についてまで、機械学習を理解する上で重要な項目が網羅的にカバーされています。
本書は機械学習をビジネスに活用することを目的に、機械学習の基礎にあたるアルゴリズムを詳しく解説しているのが特徴。具体的な例題を挙げながら、どのような考えの元で計算が行われているのかといった点がわかりやすく明らかにされています。
各アルゴリズムに共通する根本的な考え方の説明に重点を置いているのもポイント。機械学習やデータサイエンスの本質を把握しやすく、より高度な知識へ応用できる知識が学べます。見やすさにこだわったオールカラーの紙面もおすすめポイントです。
AIの学習におすすめの本|上級者向け
技術評論社 コード×AI ーソフトウェア開発者のための生成AI実践入門
AIの活用方法を、ソフトウェア開発の現場目線で提案していく実践的な指南書です。生成AIを使ったコード生成やコードリーディング支援を、実際どのように開発現場で取り入れていけばよいのかが学べる1冊になっています。
エンジニアリングにおける生成AIの現在の状況から言及。プロンプトの実例やAIと協働するためのコーディングテクニックなど、具体的な視点が全9章で紹介されています。AIを業務に活かしていくために必要なスキルや考え方の方向性を理解できるのが魅力です。
AIを業務に取り入れることを前提に、AIの力を最大限に引き出すための戦略や方法論を知りたい方におすすめの本書。現在、本格的にコーディングに携わっているエンジニアやAIを活用していきたい経営層の方はぜひチェックしてみてください。
インプレス 第3版 Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践
AIにとって重要な機械学習をテーマにした解説書の世界的ベストセラー。分類・回帰問題から深層学習・強化学習まで、機械学習に関連する知識を徹底的に解説しているのが魅力です。各手法の考え方や理論的な背景が上級者向けに詳しく説明されています。
初歩的な線形回帰から、ディープラーニング・敵対的生成ネットワーク・強化学習までを全18章で細かく章立て。scikit-learn・TensorFlow2などのPythonのライブラリを用いた、実際のコーディング手法もあわせて紹介されています。
第3版の本書では内容の多くを刷新。より現代の状況に沿った解説へとアップデートされました。AIの機械学習プログラミングを本格的に学びたい方、実践的な知識を身につけたい上級者におすすめの1冊です。
翔泳社 仕組みからわかる大規模言語モデル 生成AI時代のソフトウェア開発入門
生成AIに欠かせない技術である大規模言語モデル・LLMを体系的に学べる参考書です。大規模言語モデルの基礎的な仕組みからソフトウェア開発の手法まで、幅広い知識がわかりやすく整理されています。
Transformerの仕組み・学習プロセス・プロンプトエンジニアリングなどの基礎的な技術から解説。大規模言語モデルを用いた効果的な開発手法を学べます。Pythonによるコード例が数多く掲載されており、実践的なスキルを身につけられる1冊です。
各章がテーマ別に独立しているため、気になる箇所から拾い読みできるのもポイント。各項目の関連性もわかりやすく、自分にとって足りない知識を把握しやすい構成になっています。大規模言語モデルに関する最近の学習本を探している方は、ぜひ手に取ってみてください。
翔泳社 AIエンジニアのための機械学習システムデザインパターン
機械学習で開発したモデルをビジネスやシステムに組み込み、効果的に運用するための方法について説明した学習本です。AIを組み込んだ実装モデルをデザインパターンとしてまとめ、それぞれを詳しく解説しています。
モデルをシステムに組み込むための具体的な設計や実装方法に焦点を当てているのが特徴。機械学習システムのグランドデザインやPythonを使った実装例が多数挙げられています。機械学習を本番で活用するための方法論・運用・改善ノウハウを学べる1冊です。
機械学習運用の一連の流れが、構造設計やコードなどを盛り込みながら解説されています。取り上げられているデザインパターンのサンプルコードをダウンロードできるのも魅力。AIの機械学習を実用化する方法や運用ノウハウを学びたい方におすすめです。
講談社 深層学習 改訂第2版
ディープラーニングについて詳細に解説したベストセラー本の改訂版です。ディープラーニングの基礎的な技術について、数式とともに詳細に解説しているのがポイント。実用性を重視した上で、ディープラーニングの手法が網羅的に取り上げられています。
ネットワークの基本構造から、確率的勾配降下法・誤差逆伝播法・畳み込みニューラルネットワークなどの基本技術を具体的にピックアップ。それぞれの理論面が詳しく説明されており、ディープラーニングについてより学びを深めたい方におすすめです。
AIにおけるディープラーニングを学びたい方の定番書として定評がある本書。第2版では近年の話題についても大幅に追加収録されました。ディープラーニングの研究に携わりたい方にも適した学習本です。





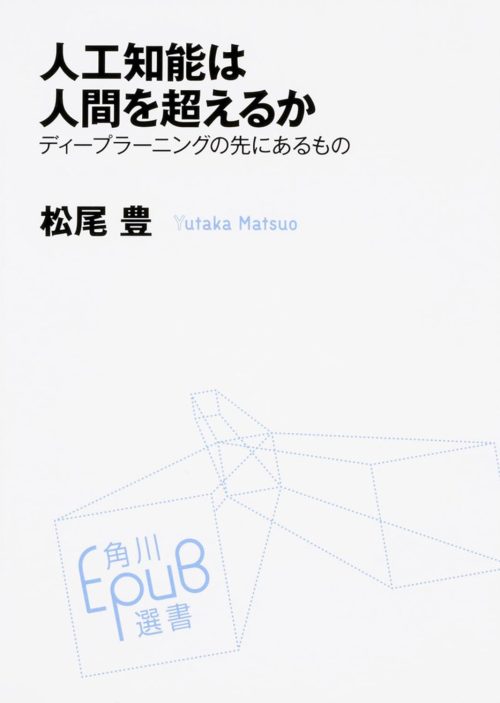
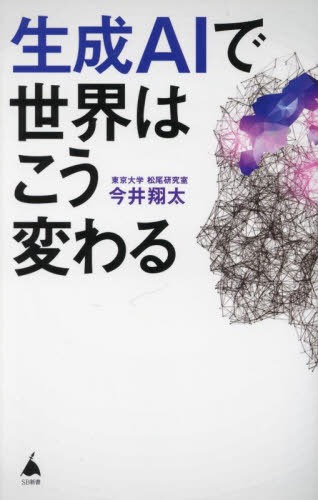
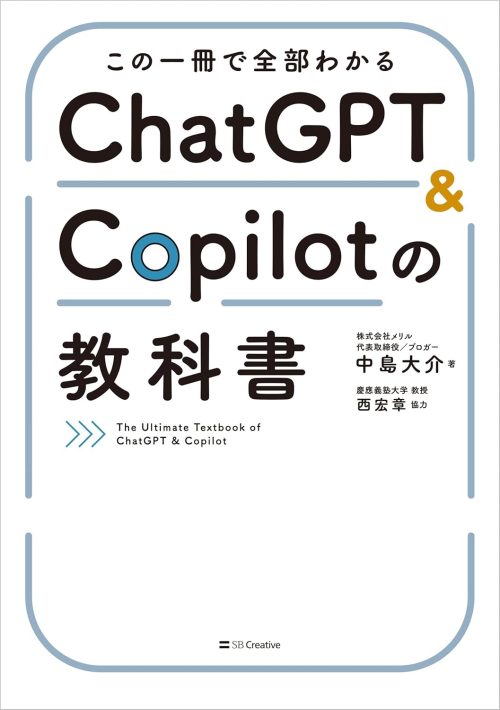

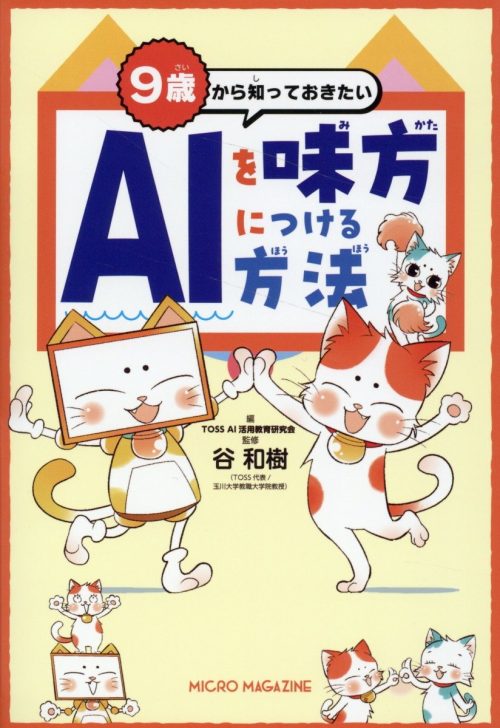
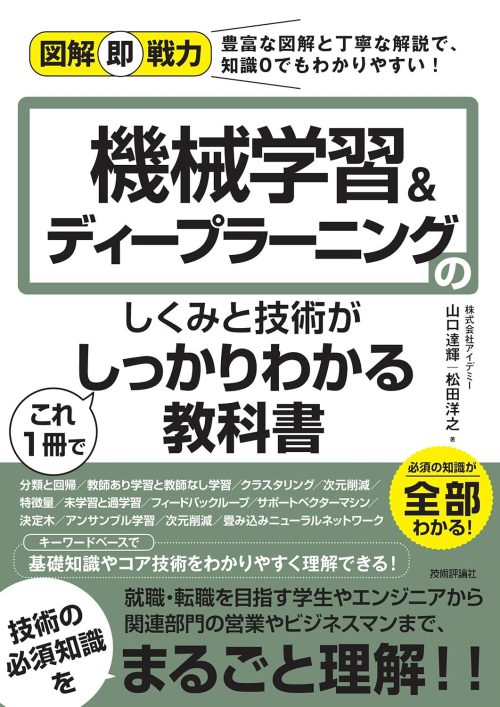
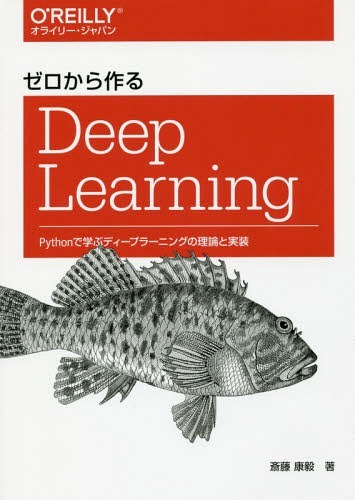
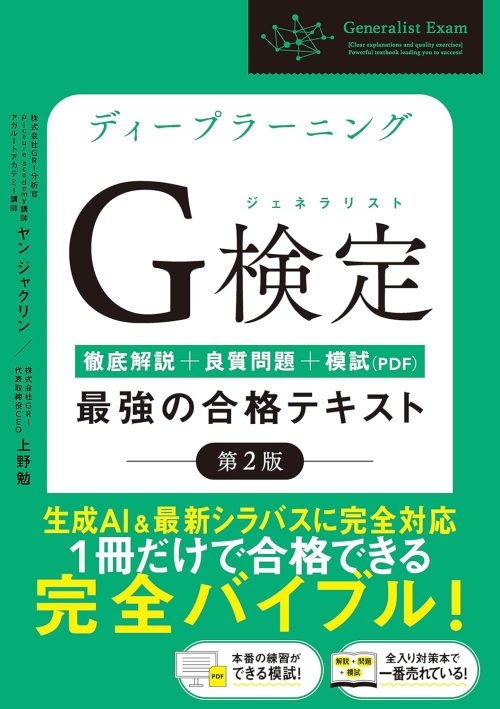
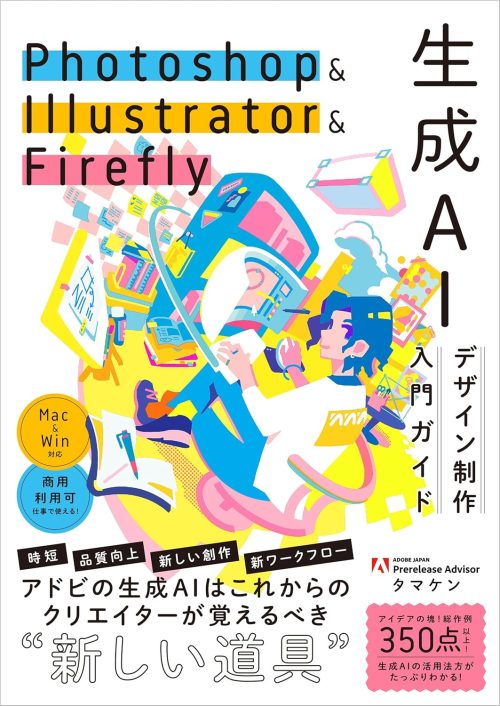
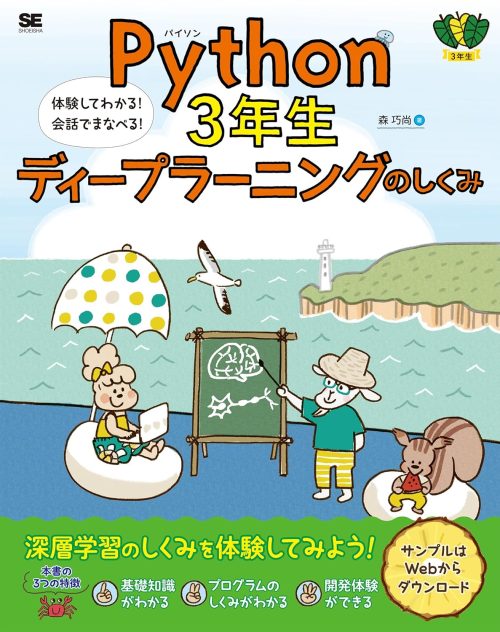
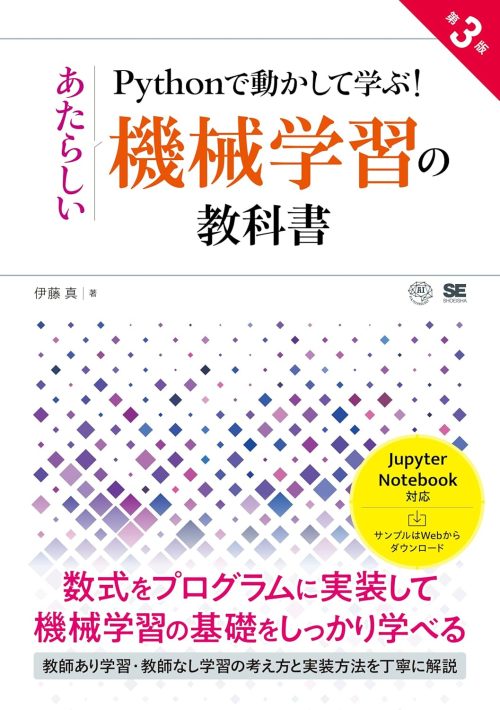
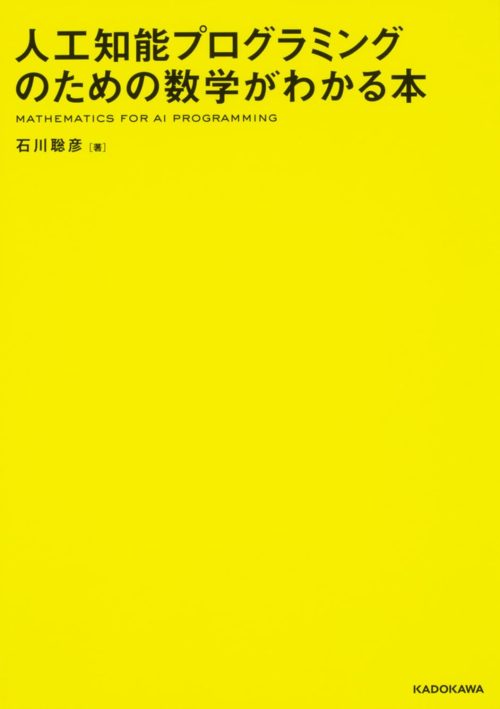
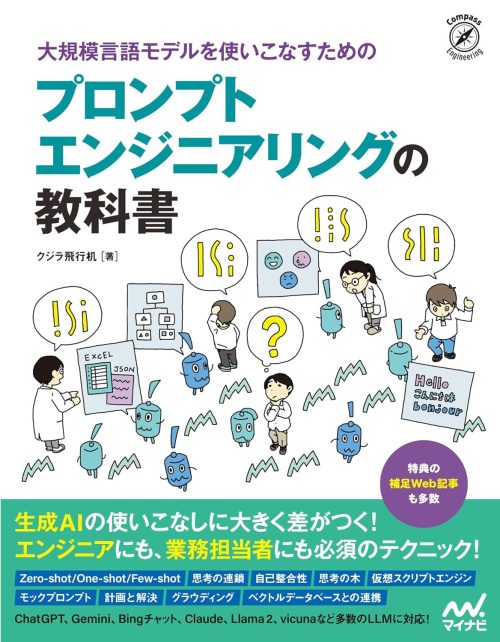
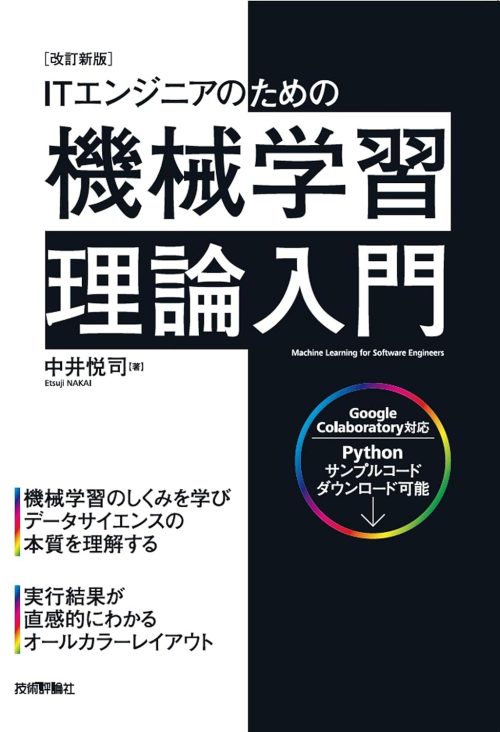
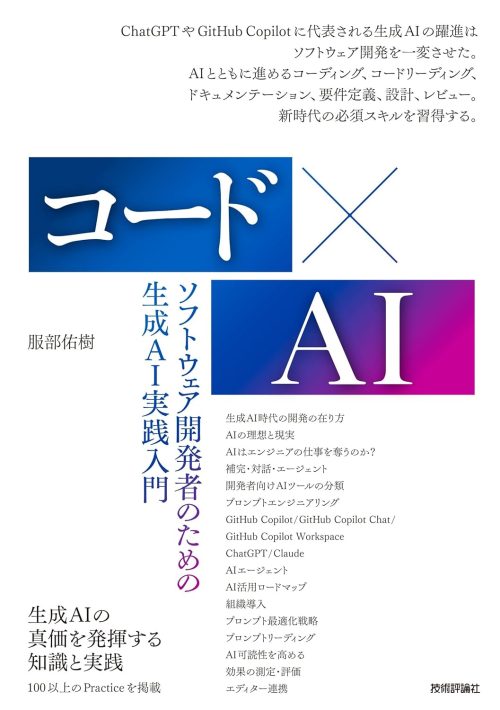
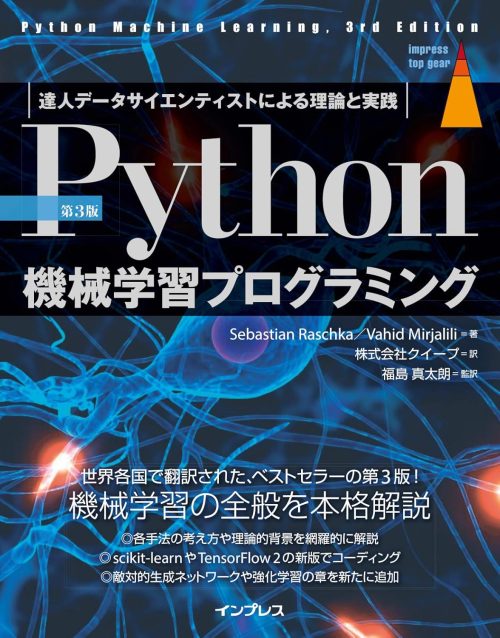
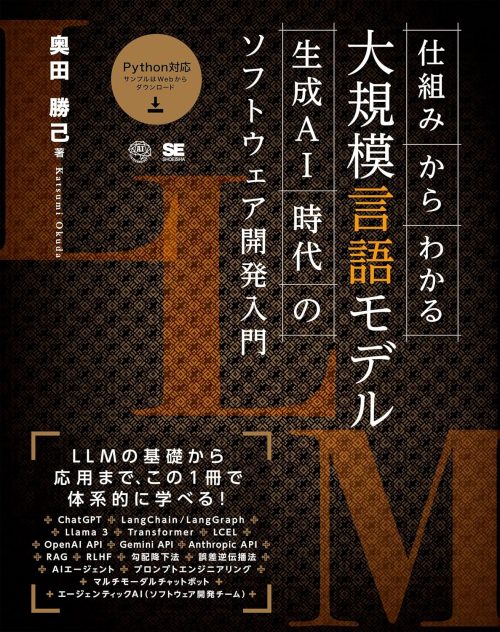
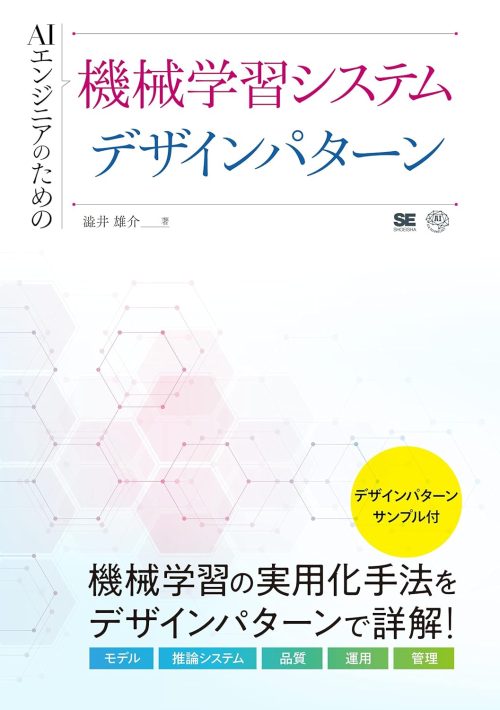
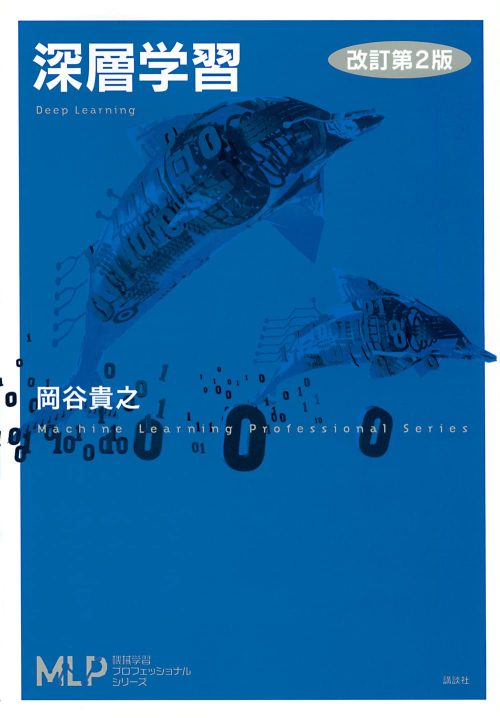

















ひと口にAIの学習本といっても、紹介されている内容のレベルや本のテーマは多岐にわたります。まずは自分の知識レベルにあわせて、最後まで読み通せそうな本からステップアップしていくのがおすすめ。AI利用の目的が定まっているなら、知りたい内容が書かれているモノに絞りながら複数の本で深掘りしてみてください。