身の回りのお金の問題や国の経済政策について深く考えられるようになりたいという方は、経済や経済学をテーマにした本を読むのがおすすめです。難しい概念や用語がわかりやすく解説されており、自らさまざまな情報を読み解いて考える力を養えます。
今回は、数ある経済・経済学の本のなかからおすすめをご紹介。経済と経済学の違いを踏まえながら、自分に適した本の選び方についても解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
まずはAmazon Kindleのセール&キャンペーンをチェック
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。最新情報につきましては、Amazonページにてご確認ください。経済・経済学のおすすめ本の選び方
経済と経済学の違いを理解する

自分の目的に合った経済・経済学の本を選ぶためにも、まずは経済と経済学の違いを理解しておくことが重要です。「経済」とは、人間の生活に必要なモノやサービスを生産し、分配・消費する社会的な活動や流れのことを指します。
一方で「経済学」とは、社会のさまざまな経済活動・経済現象を科学的に研究する学問のこと。社会全体の動きや個人の意思決定における法則性を客観的に分析し、生活をよりよくするための方法や手段について考えることが主な目的です。
お金・景気・投資といった、現代社会に欠かせない経済活動について広く理解したい方は、経済をテーマにした本を手に取るのがおすすめ。経済活動の裏で用いられている具体的な考え方や指標を知りたい方は、経済学の視点を学べる本から選んでみてください。
自分のレベルに合った本を選ぶ

経済・経済学の本を選ぶ際には、自分の知識レベルにマッチしたモノを選ぶのがおすすめです。ひとくちに経済・経済学の本といっても、解説されている内容の深さは製品によってさまざま。特に経済学を扱ったモノでは専門用語も数多く登場します。
経済・経済学の初歩的な知識から学びたい方は入門をコンセプトにしたモノをチェック。例や図解などを多く盛り込んだり、物語形式の説明を取り入れたりと、難しい概念を噛み砕いたわかりやすい解説が魅力です。
ある程度、経済・経済学の前提知識を理解できたら、より具体的で実践的な内容を掘り下げたモノへとステップアップしていくのがおすすめ。テーマや目次などを参照し、無理なく読み通せそうな内容かどうか確認してみてください。
興味のあるテーマや視点から選ぶのもおすすめ

経済・経済学の本は、興味のあるテーマや視点を重視して選ぶのもおすすめです。経済・経済学は対象になる領域が広く、1冊で全てを把握しきることが難しい分野。テーマや視点を絞ることで、自分の知りたい情報を解説した本を見つけやすくなります。
近代の経済学では、主に「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」の2つの視点に分けて考えられています。ミクロ経済学とは、個人や家庭の消費行動や企業の経済活動に焦点を当てた学問。一方のマクロ経済学は、日本や世界といった大きな視点で経済活動を捉える学問です。
モノやサービスの価値がどのように決定されるのか、資源を効率的に活用するにはどうすればよいのかといった、細かな法則を知りたい方はミクロ経済学の本がおすすめ。景気と政治の問題や市場全体の動きなど、経済を大局的に理解したい方にはマクロ経済学を扱った本が適しています。
経済・経済学のおすすめ本
サンクチュアリ出版 東大生が日本を100人の島に例えたら 面白いほど経済がわかった!
難しい経済の仕組みをシンプルに噛み砕いて説明した、経済のおすすめ本です。「日本がもしも100人の島だったら?」という想定をベースに解説しているのがポイント。スケールが大きい経済の全体像を掴みやすい構成が採用されています。
国とお金の関係・景気と物価・経済の課題と未来についてまで、全7章立てで経済に関する知っておきたい知識を網羅。それぞれの項目が「100人の島で起きた出来事」として、寓話的にたとえられています。
金利・国際・為替・インフレといった基本的な用語からていねいに説明。経済についてまったく知らなかったという人も、自分の意見を持てるようになることを目的としています。中学生・高校生も読みやすい経済の本です。
KADOKAWA 大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる
20年以上、東京大学で経済学を教えてきた著者が、経済学の基本的な知識を凝縮して解説した入門書です。大学4年間で学ぶ経済学の大まかな枠組みを全3章・20項目に分けて説明。ミクロ経済学やマクロ経済学の考え方の基本を初心者も手軽に学べます。
消費者・企業の行動と経済との関連、市場の機能と価格メカニズムといったミクロ経済学の視点から順序立てて解説。後半では国の経済成長や金融政策、マクロ経済政策についてまで、経済学の一連の知識が幅広く紹介されているのが特徴です。
教養として必要とされる経済学の知識を、1日30分の読書で学べると謳われる本書。経済学を学ぶにあたって基本として知っておきたいキーワードが網羅されています。いちから経済学の知識を身に付けたいという人におすすめの1冊です。
KKベストセラーズ 目からウロコが落ちる 奇跡の経済教室 基礎知識編
“読まれると経済学者・官僚が困る本”をコンセプトに、日本経済の本質を暴く解説が魅力の経済本です。大きく全2部に分けて、経済の基礎知識と日本経済を取り巻く実状について詳しく触れていきます。
経済政策の問題点、金融と財政にまつわる勘違い、税金の実像といった、日本経済を考えるうえで知っておきたい本質的な知識を解説しているのが特徴。一般的に常識と思われているような数々の言説に鋭く切り込んでおり、経済の捉え方に新たな視点を与えてくれます。
続編も刊行されており、基礎知識編である本書からより詳しい内容へと知識を深めていけるのもポイント。今後の日本経済のあり方を考えていくための、具体的な知見を得たい方におすすめの1冊です。
すばる舎 若い読者のための経済学史
経済学の原始から現代に至るまでの歴史をテンポよく紹介していくおすすめの経済本。さまざまな学問分野の概要や背景を解説する「リトル・ヒストリーシリーズ」の、経済学をテーマにした1冊です。
経済学とは何か、どのように発展してきたのかといった流れが、全40編で簡潔にまとめられている本書。古代ギリシャの哲学者に始まり、アダム・スミスからトマ・ピケティまで、経済学において重要な人物の思想と経済学における意義が広く取り上げられています。
各人物や流派については深く掘り下げすぎず、現代の経済・経済学との関連がわかりやすいよう構成されているのが魅力。経済史家・政治経済ジャーナリストである著者の面白い洞察や見解も見どころです。経済学史の概要を知りたい方はぜひチェックしてみてください。
Gakken 経済評論家の父から息子への手紙 お金と人生と幸せについて
インデックス投資の知名度を高めた著者が、大学生の息子にあてて書いた手紙をもとに執筆された経済の本です。経済と上手く付き合っていくうえで役に立つ「明るい人生のマニュアル」をコンセプトにしています。
お金の心配に振り回されずに生きていくための戦略が数多く紹介されているのが特徴。これからの時代の働き方・稼ぎ方、資本主義経済の仕組みを踏まえたお金の増やし方など、著者ならではの日本経済論と人生論が語られています。
個人レベルのミクロな経済活動から、社会に焦点を当てたマクロの経済活動まで目を向けている本書。人生を豊かに生き抜くための著者なりの幸福論が、語りかけるような文体で綴られています。これから社会へと出ていく高校生・大学生への贈り物にもおすすめです。
KADOKAWA お金の流れでわかる世界の歴史 富、経済、権力……はこう「動いた」
元国税調査官の著者がお金の流れに着目して世界の歴史を紐解いた、経済のおすすめ本です。国の繁栄と衰退、文化の広がりなどに隠された経済の関わりを探る1冊。全12章で、さまざまな時代・地域の経済の様子や裏話が解説されています。
脱税で滅んだ古代ローマ、金融破綻で敗れたナポレオンなど、世界史において重要な出来事に経済がどのように関連していたのかを深掘りしていくのが見どころ。人類史5000年にわたるお金・経済・権力の動きが、順を追ってユーモラスに解説されています。
現代にも共通する経済事象が、歴史に絡めてわかりやすく取り上げられているのが魅力。徴税や為替といったシステムが、歴史のなかでどのように発展してきたのかが垣間見られます。お金の影響力を考えるきっかけとしても楽しめるおすすめの入門書です。
東洋経済新報社 きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」
お金に関する不安や疑問を、物語形式で解説していく話題の経済本です。日本の借金問題や物価の上下、老後資金の不安など、お金と経済にまつわる身近な6つの疑問を提示。お金の本質と社会の成り立ちを、物語のなかでシンプルに紐解いていきます。
中学2年生の少年・優斗と投資銀行勤務の七海が、ある大富豪から講義を受ける形式で進んでいく本書。難しく感じられる経済の問題を簡潔に説明し、人生と社会を豊かにするためにお金とどのように関わっていくべきかが提案されているのが特徴です。
いかにお金を増やすかという点ではなく、お金に振り回されて生きないための考え方に焦点が当てられています。経済について予備知識がなくとも読み進められる構成になっているのが魅力。読書が苦手な方にもおすすめの1冊です。
筑摩書房 高校生のための経済学入門 新版
高校生が自分で経済ニュースの内容を理解して考えられるよう、経済学の考え方を噛み砕いて説明した入門書です。重要なポイントやキーワードを押さえながら、全7章で経済学の全体像を掴める構成になっています。
現実のさまざまな経済問題を解決するために、経済学の考え方をどのように生かせばよいのかが分かる1冊。GDP・金融政策・累進性・マネタリーベースといった、知っていても説明しづらい経済用語をしっかりと理解できる明快な解説文が魅力です。
経済学の理論を知るだけでなく、実際に活用できる考え方を身につけることを目的としています。新版の本書では、検索性を高めるキーワード索引が設けられているのもポイント。ビジネスパーソンの学び直しにもおすすめです。
あさ出版 たった1つの図でわかる! 図解 新・経済学入門
難しい理論は省略し、1つの図のみを用いて経済をわかりやすく説明した経済・経済学のおすすめ本。図を読み解いていくことで、現代の世の中で起こっている経済のさまざまな要素を掴める構成になっています。
ミクロ経済学を用いたモノの値段の決め方や金融政策、財政政策など、経済学において重要な項目を全4章立てでピックアップ。それぞれ豊富な具体例を交えながら解説されているのが特徴です。
経済を考えるにあたって重要な物価変動と経済政策についてが、図を通して簡潔に整理されています。経済知識に馴染みがない方も経済ニュースを自分の頭で読み解き、意見を持てるようになることを目指したおすすめの1冊です。
早川書房 予想どおりに不合理
さまざまな経済現象を、心理学の知識やデータを絡めて分析する行動経済学をテーマにした名著。”行動経済学ブームに火をつけた”と評されるベストセラーです。人間が合理的ではない行動をとる多彩な理由が、面白い実験の内容とともに解説されています。
「現金は盗まないが鉛筆なら平気で失敬する」「頼まれごとならがんばるが安い報酬ではやる気が失せる」など、人間にありがちな不合理な行動の数々に着目。その裏にどのような心理が働いているのかを解説した1冊です。
専門用語が少なく、わかりやすい実験例が多数挙げられているため、行動経済学の初学者でも楽しみながら読みやすいのが魅力。日々の意思決定や行動にありがちな謎の理由を知り、経済活動に活かすための視点を学べるおすすめの経済の本です。
SBクリエイティブ 行動経済学が最強の学問である
行動経済学の主要な理論をビジネスパーソン向けに初めて体系化した1冊。行動経済学がビジネス界において注目を集めている理由に触れながら、行動経済学の基礎知識から具体的な理論までをていねいに解説していきます。
行動経済学に用いられる理論を「認知のクセ」「状況」「感情」の3つの視点に分けてるのが特徴。それぞれの理論を単体で把握するだけでなく、相互的にどのように影響を与えるのかまで理解できる構成になっています。
行動経済学を俯瞰的に捉えているのが本書の魅力。消費者や投資家として非合理的な決定をしてしまうメカニズムを知り、行動経済学の本質に触れることを目的としています。ビジネスに活かせる、世の中のさまざまな仕組みを学びたい方にもおすすめです。
かんき出版 スタンフォード大学で一番人気の経済入門 マクロ編
アメリカのスタンフォード大学にて最優秀講義賞を獲得した授業を再現する形で制作された経済学の本です。経済成長や国際収支について考えるマクロ経済学に特化した1冊。ほかにも、ミクロ経済学版も刊行されています。
経済全体を国や世界単位で大きく捉え、分析するためのマクロ経済学の考え方を初学者向けにていねいに解説。「マクロ経済とGDP」「経済成長」「失業率」「インフレ」「国際収支」の全5章を通して、マクロ経済学に必要な視点を広く学べる1冊です。
難しい専門用語は表現を置き換えて説明していたり、具体例を示していたりと、細かな配慮がちりばめられています。経済学の知識に自信がない方でもマクロ経済学について学び始められるおすすめの人気作です。
ダイヤモンド社 「原因と結果」の経済学 データから真実を見抜く思考法
近年の経済学の分野で注目されている「因果推論」の考え方を、日本の一般書で初めて紹介した1冊。因果推論とは2つ以上の事柄の原因と結果の因果関係を、データを用いて分析する手法のことを指します。
世の中にある根拠のないさまざまな通説を例に挙げながら、因果推論の考え方をやさしく解説していくのが本書の特徴。「ランダム化比較試験」「差の差分析」といった、因果関係を証明するさまざまな手法の活用方法がわかりやすく解説されています。
解説には数式などを使用していないのもポイント。複雑な因果推論の概要を掴み、学習の基礎になる知識を学べます。データを正しく利用するための思考法を身につけるのにも役立つ、おすすめの経済学の本です。
東京化学同人 マンキュー 入門経済学 第4版
“世界中の大学で最も読まれている経済学の教科書”として謳われている1冊。経済学の入門をテーマにした本書にはじまり、「ミクロ編」「マクロ編」へと深掘りしていけるおすすめの経済学の本です。
経済学の10原則から、ミクロ経済学・マクロ経済学の両方の概要まで幅広く解説されたボリューミーな入門書。付録の補論では、経済学者が実際にどのようにデータを活用しているのかにも触れられています。
ハーバード大学の教材としても採用されるほどのハイレベルな内容ながら、明快でわかりやすい語り口で解説されているのがポイント。経済学を本格的に学んでいきたいという方の指針になる、おすすめの1冊です。
日本評論社 ミクロ経済学の力
“ミクロ経済学教科書の決定版”と謳われるミクロ経済学に特化した専門書です。ミクロ経済学を学ぶにあたっての基盤になる、市場メカニズムがしっかりと理解できるよう構成されているのが魅力。経済学の本質的な内容を捉えられます。
第1部では価格理論を取り上げ、市場メカニズムの特徴と問題点について言及。第2部では、現代の経済学の新しい流れであるゲーム理論について詳しく解説されています。図解を豊富に盛り込み、直感的に理解しやすいのもメリットです。
理論を裏付けるような実例が豊富に挙げられているのがポイント。各項目で必要な数学の手法についても、あわせて解説が掲載されています。
経済・経済学のおすすめ本の売れ筋ランキングをチェック
経済・経済学のおすすめ本のランキングをチェックしたい方はこちら。





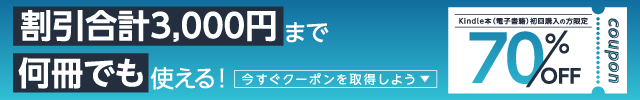

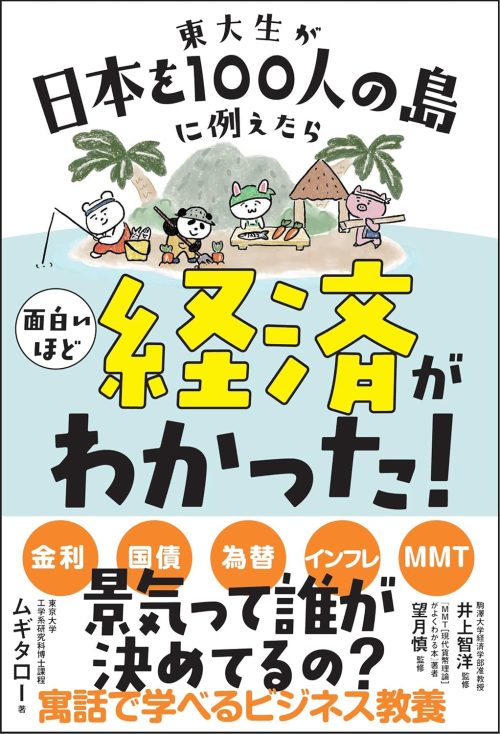
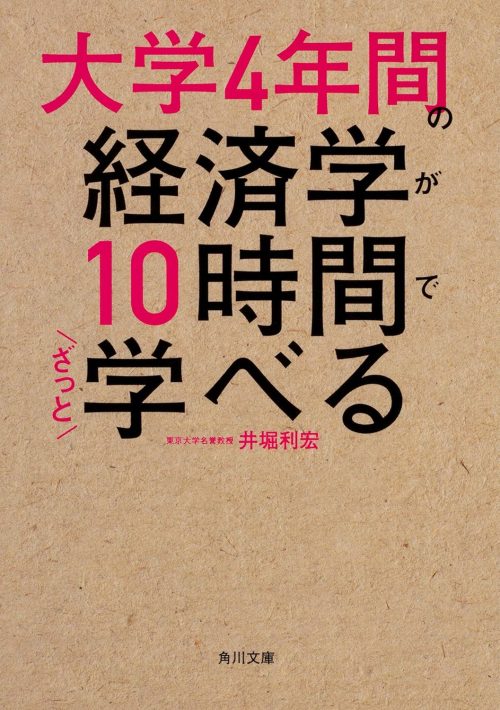
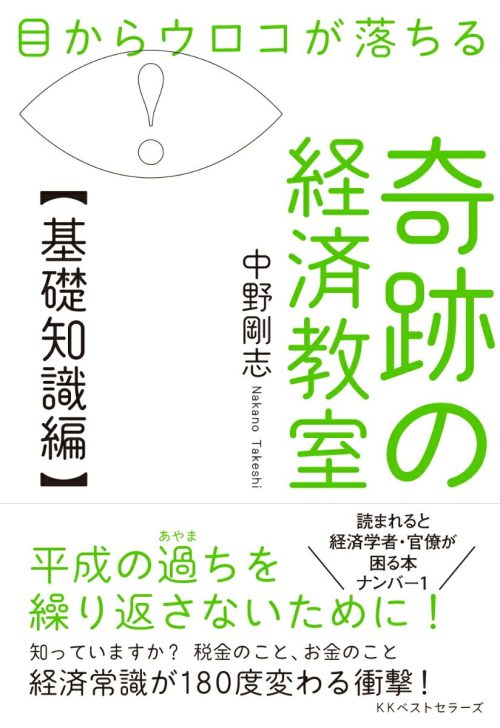
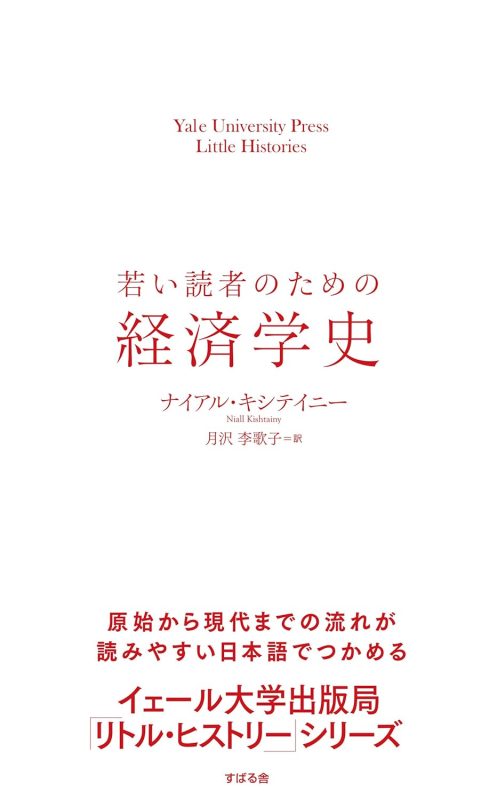
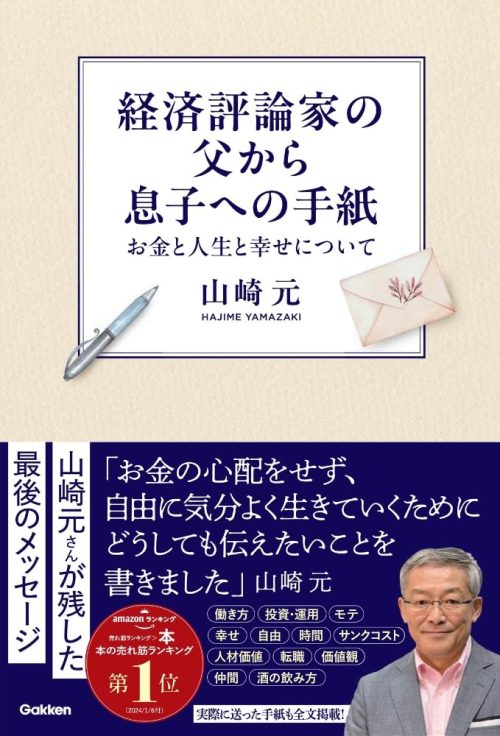
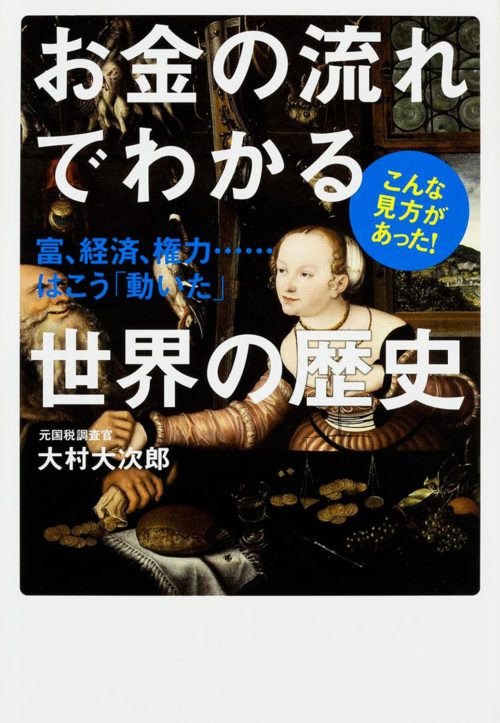
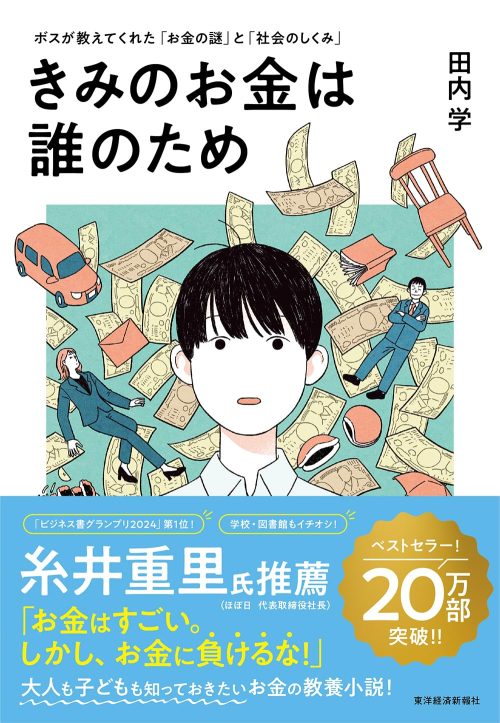
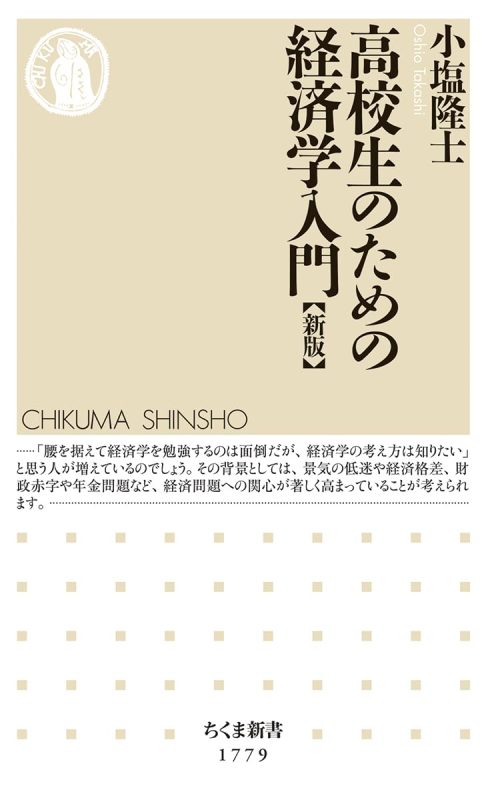
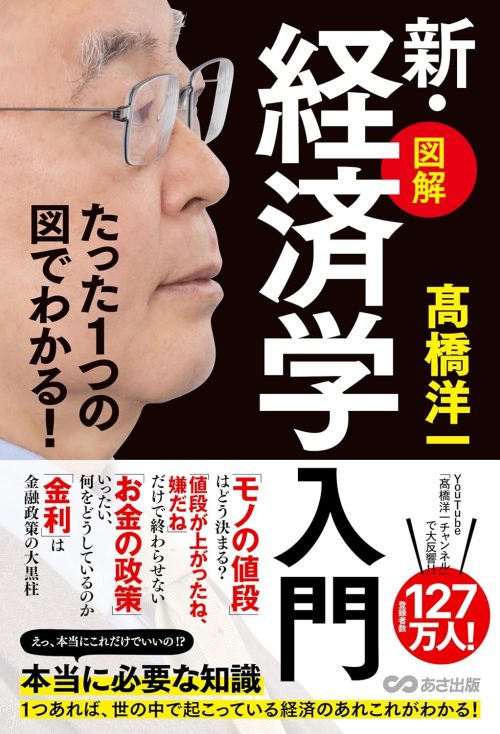
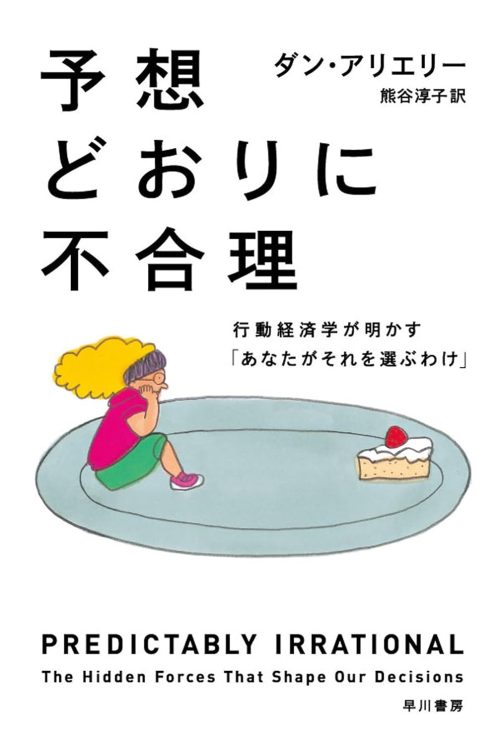
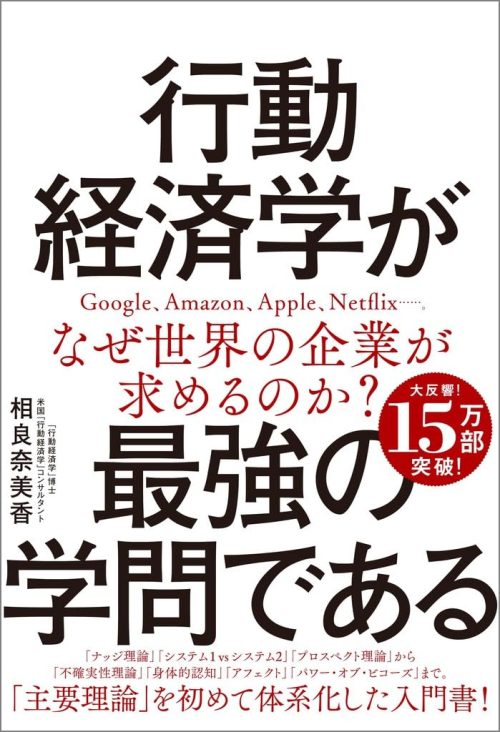
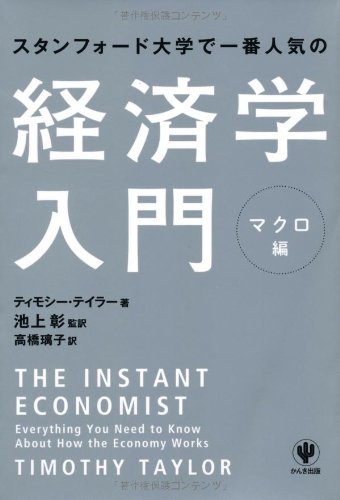
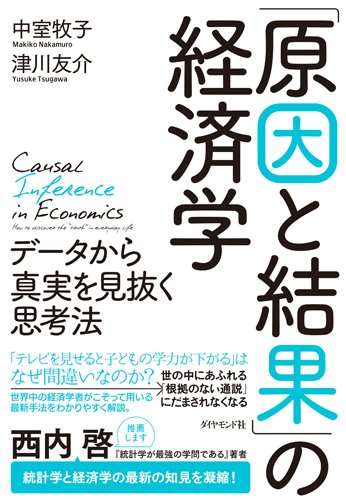
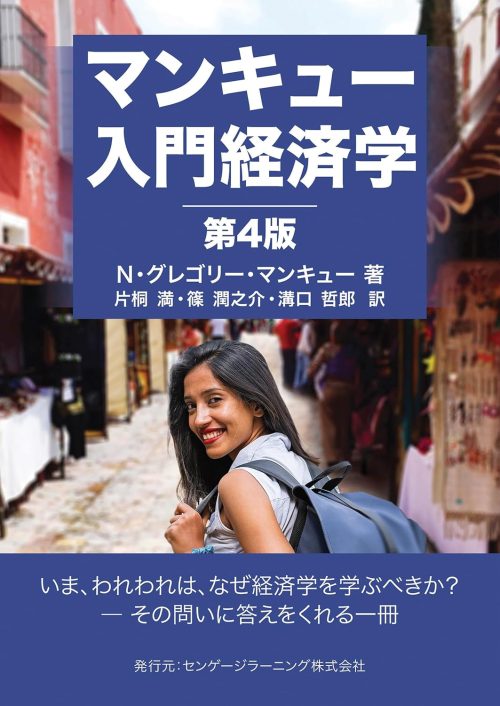
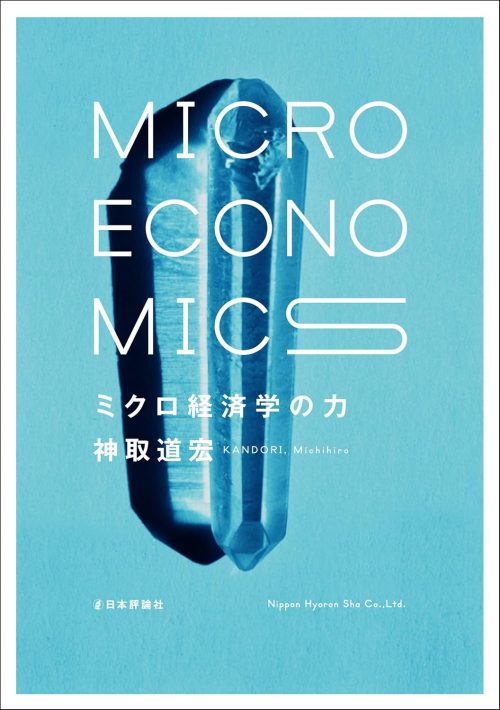

















生活とは切り離せない経済について学ぶことで、社会や政治に対する理解を深められます。経済・経済学は領域が広いため、自分の知りたい情報や知識レベルに適した本を選ぶことが重要。中高校生も読みやすい入門書からステップアップしていくのもおすすめです。気になる本を手に取って、学びの一歩を踏み出してみてください。